いつもElusaMaat(エルサマアト)のブログを見て頂きありがとうございます。
今回は広島県安芸郡府中町に「多家神社」の紹介です。

ちょっと階段が急で、子供だけでは少し怖いかも。


手水舎(てみずしゃ)

ここも本当に気持ちのいい空間です。

この多家(たけ)神社(別名 埃宮(えのみや))
神武天皇が日本を平定するため、お立ち寄りになったと伝わってます。
古事記では、阿岐国(安芸国)《あきのくに》の多祁理宮(たけりのみや)
に神倭伊波礼毘古命《初代神武天皇》(かむやまといわれびこのみこと)が
七年いたといわれます。日本書紀には埃宮(えのみや)に坐すと記して
あります。
安芸国の名神大社三社の1つとして多家神社の名が記され、
伊都岐島神社《厳島神社》(いつきしまじんじゃ)、
速谷神社とともに全国屈指の大社とあがめられたとあります。
厳島神社は皆さんもご存じ、宮島にある平清盛が再建した神社です。
速谷神社は、車のお祓い神社として広島では有名です。
すげ~神社が近くにあったんだ~と。
ここの神社は、職人時代よく昼休憩にベンチで休ませて頂いてました。
広島県の指定重要文化財に指定されいる建物が

この宝倉。
通常は三角の木を組んで周囲の壁を形成するのですが、
この宝蔵は不等辺六角形の木を組んだ珍しいもので、
あまり例を見ないそうで、日本に現存するものでは
当宝蔵だけみたいです。

御神札・御守授与所
ここにこんなのが有ります。

神武天皇には「八咫烏(やたがらす)」と「金鵄(きんし)」は
セットで登場しますね。
八咫烏(やたがらす)
八咫烏(やたがらす、やたのからす)は、日本神話に登場するカラス(烏)
であり導きの神。神武東征の際、高皇産霊尊(タカミムスビ)によって
神武天皇のもとに遣わされ、熊野国から大和国への道案内をしたとされる。
一般的に三本足の姿で知られ、古くよりその姿絵が伝わっている。金鵄(きんし)
金鵄(きんし)は、『日本書紀』に登場し、
神武天皇による日本建国を導いた金色の鵄。
日本書紀の記述では、東征を進める彦火火出見(後の神武天皇)
が長髄彦と戦っている際に、金色の霊鵄が天皇の弓に止まると、
その体から発する光で長髄彦の軍兵たちの目がくらみ、
東征軍が勝利することができたとされる。
この霊鵄を指して「金鵄」と呼ぶ。ウィキペディア(Wikipedia)より
調べると色々なことが分ります。

この位置から広島市内が見えます。
景色は全く違いますが、神武天皇もここに居られたと思うと
不思議な感じがします。
こんな身近な所に、初代神武天皇にまつわる神社があるなんて
知りもしませんでした。
とてもいい所なので、広島に来られた際は是非お立ち寄り下さい。




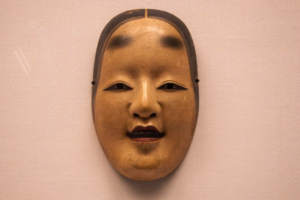








コメントを残す